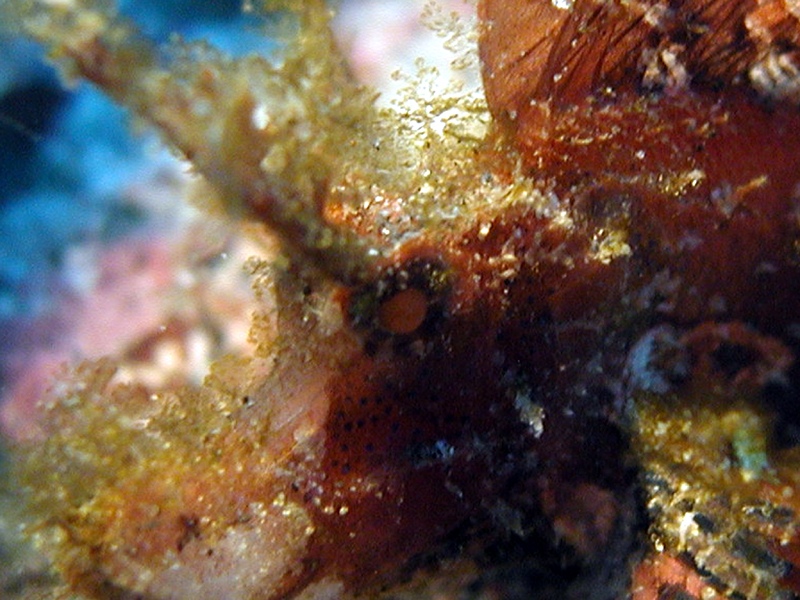ヒッポスコルパエナ・フィラメントサ(イトヒキカサゴ)
2007年年末、大瀬崎を大きくにぎわせていた生物がいました。それが、この学名「ヒッポスコルパエナ・フィラメントサ」ローマ字で書くと「Hipposcorpaena filamentosa」。正直舌を噛みそうで、ソラでは決して言えない魚の名前なんですが(大瀬の人は、「フサカサゴの一種」って言ってました)、まあ非常に珍しい魚(世界でも発見例が少ない極レア種)なんだそうで、この寒い中、土日なんかはえらい行列が出来ているという事で、会社を休んで平日に行ってきました。(一緒に行った友人も会社休んでました。いい人だ)
でも張り切りすぎたのか、あの人がごった返している大瀬崎のビーチにスタッフあわせて一桁の人数しかいませんでした。。。大瀬ってこんなに広かったのね…。
お陰で撮影はほぼ独占状態で周りにも人っこ一人いませんでした。ラッキー。
まあ、なにんしろ多分この一生でもう合うことがない種なんだろうなぁと思います。
分類的にはフサカサゴ科なんですが立派なツノが2本突き出ています。そしてツマジロです。また下でも書きますが、ガラス目で、足があり、なんか珍しい上に、それだけでは飽き足らず、同類の他の魚の特徴の良いとこ取りしてます。キン肉マンの悪魔将軍みたいなヤツです(わかりにくっ!)。
個人的には正面からのこのカットが1番気に入ってます。
もう一つ特徴があって、それは尻ビレと体の下側のヒレに黒と黄色の綺麗な斑紋があることです。大瀬崎のカメラダイバーは、そのヒレをバッチリ広げた所を撮って何ぼのようです。
そんな状況累計1時間いましたが、微塵も見せる様子無く、私が撮れたのは、この移動中にわずかに翻った時の一枚くらいでした。(これまた、わかりにくっ!)
これがその足です。正確にはヒレなんでしょうが。。。この足を前後にチョコマカ動かして、前進します。
言うなればホウボウと同じような感じで動くというと分かりやすいでしょうか?
で、やっぱり思うのはこの一言、
魚なんだから泳げよ(笑)
目はガラス目と言いましょうか、お椀に水を張ったような目です。キラキラしていて、こちら側が鏡のように反射して見えそうです。
この目どこかで見たことがあるなぁと思って陸に上がってふと思い出しました。ハダカハオコゼの目にソックリでした。う~んやるなぁこの色男。
名前の由来については、学名「filamentosa」が示す通り、体の一部に糸状(フィラメント)の突起があることから名付けられたと考えられます。この特徴的な突起は、他のカサゴ類と区別する際の重要なポイントとなります。また、和名がそのまま学名を音写したものになっている点も興味深いです。
スキューバーダイビングの観点から見ると、この魚は非常にユニークな存在です。体長は4~7cm程度と小型ながら、立派なツノ状の突起やガラス質の目が目を引きます。岩場や砂地に擬態して隠れていることが多いため、発見には観察力が必要です。特に、フィラメント状の突起や体色の微妙な変化を見逃さないことが重要です。
他の種との見分け方としては、このフィラメント状の突起や独特な体形が挙げられます。同じフサカサゴ科でも、例えばキリンミノなどとは胸ビレや体表模様が異なるため、注意深く観察することで区別が可能です。
ヒッポスコルパエナ・フィラメントサは、その珍しさと美しさからダイバーに人気の魚種ですが、生息域が限られているため、出会える機会自体が貴重です。観察する際には環境への配慮を忘れず、自然との調和を大切にしたいものです。